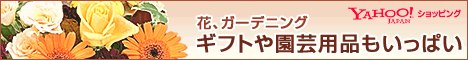こんにちは、サシャ(@sashalog_com)です。
今回は「グランドカバーになる植物」についてのお話です。
我が家では花壇や無駄に広い敷地内で縦横無尽に育つ雑草対策として、様々な種類の植物をグランドカバーとして利用しております。
敷地内の雑草は定期的に草刈機で刈ってはいるのですが、刈るのも一苦労。
放置するわけにもいかず、せめて刈る回数を減らせないものかと、雑草を抑え込める植物をいくつか育てておりますので、ご紹介したいと思います。
グランドカバーとは

グラウンドカバーとは茎や枝が地面や壁面などを覆うように育つ植物の総称で、地被植物とも呼ばれております。
主に匍匐性のものが使用され、植えっぱなしであまり手がかからない植物が多いことが特徴です。
庭や花壇の空いている場所にグランドカバーを植えておくと、雑草が生えにくくなり綺麗な状態を保つことができるのですが、我が家は寒冷地にありますので、グランドカバーとなる植物は耐寒性があるものを選んでおります。
グランドカバーに向いている植物の中には這うように育つもの以外にも、少し高さがあるもの、葉が大きかったり小さかったり、花が咲くものや実ができるものまで様々な種類があります。
強健で丈夫なグランドカバー
マンネングサ(セダム)

ベンケイソウ科マンネングサ属に分類される植物の総称・マンネングサ (万年草)。
マンネングサとは多肉質で常緑な葉を持ち、丈夫でいつまでも枯れないことから付けられた名前ですが、園芸ではセダムと呼ばれる事が多く、我が家でもセダムと呼んでおります。
セダムは乾燥に強い植物で、山地や海岸地の岩上をはじめ、下記画像のようなコンクリート上であっても、そこにわずかな土があれば根を張り生長できるほど強健な植物です。
性質は強健ですが、お花は星型でチマっとした可愛らしい姿をしております。

セダムには様々な品種がありますが、グランドカバーには寒さに強い匍匐性タイプが向いており、我が家ではツルマンネングサ(蔓万年草)とシンジュボシマンネングサ(真珠星万年草)の2種類を育てております。

匍匐性のセダムの草丈はそれ程高くないのですが、稀に下記画像のように凄まじい生長を遂げる場合があります。

一見すると目論見通りに雑草を抑え込んでいるように見えますが、一つ問題が。
モコモコに生長したセダムの根元を覗き込むと……、そこには大量のナメクジがおりましたとさ。
ちょっとキモい。
という事で、ナメクジは植物への食害がありますので、この場所のセダム共々おさらばとなりました。
セダムは暑さ寒さには強いのですが過湿による蒸れには弱い植物ですので、いずれ切り戻す必要があったため、丁度良かったです。
切らなければ枯れるばかりか、我が家のように湿気を好む虫たちの棲家となってしまう場合もあるようです。
なお、肥料も何も与えていない敷地内の雑草地帯で生長したセダムの高さは10cmにも満たないため、この場合は恐らく、チューリップに与えた肥料がセダムの生長に影響したものと思われます。
シロツメクサ


マメ科シャジクソウ属の多年草・シロツメクサ(白詰草)。
我が家で育てているシロツメクサは葉っぱが赤紫色の園芸品種なのですが、品種名が分かりませんので、見てそのままの「赤葉のクローバー」と呼んでおります。
この品種は気温が低い春先や秋には葉っぱの色が赤紫となるのですが、気温が高くなると緑に変化します。
草丈は15cm程ですがお花は30cm程まで生長します。
春先のシロツメクサはパヤパヤとしていて頼りなかったのですが、


3週間経った頃には下記画像のような大きさにまで生長を遂げました。


育て始めたばかりなのですが、すでに周りの雑草をあらかた飲み込んでしまっております。
頼もしいやら、末恐ろしいやら。
シロツメクサは繁殖力が半端ないため雑草扱いされる場合もありますが、我が家ではスギナやドクダミが群生するよりは100倍マシ!と考えておりますので、問題ありません。
ただし、他の植物への影響を考慮して花壇には植えず、敷地内の雑草地帯でのみ生育しております。
なお、モモコモコに生長したシロツメクサの根元を覗き込むと……、そこにはダンゴムシがおりましたとさ。
微妙な数ね……。
今のところダンゴムシによる害はありませんので処遇については保留中ですが、このように匍匐性植物の根元には虫が棲みついている場合がありますので、虫が苦手な方はご注意ください。
花も楽しめるグランドカバー
クリーピングタイム


シソ科イブキジャコウソウ属のハーブ・クリーピングタイム。
一般的にタイムと言えば立性のコモンタイムのことを指しますが、クリーピングタイムは匍匐性で、我が家ではナツメの周りの雑草対策に利用しております。
草丈は10cm程、ポワポワとした可愛らしいお花を咲かせる見た目とは裏腹に繁殖力は強めで、今日まで他の雑草を寄せ付けずにおります。
冬には地上部が枯れてしまうのですが、マイナス10℃まで耐える強靭な根を持っておりますので、我が家のような寒冷地であっても、余裕で冬を越すことができます。
なお、同じような匍匐性植物とお隣同志になりますと、縄張り争いの末に場がぐちゃぐちゃになる恐れがありますので、クリーピングタイムを使用する場合は同じような匍匐性植物とは距離をとった方が良いと思います。
セイヨウジュウニヒトエ


シソ科キランソウ属の多年草・セイヨウジュウニヒトエ(西洋十二単)。
日本に自生するジュウニヒトエの近縁種で、セイヨウキランソウとも呼ばれておりますが、園芸界ではキランソウ属に分類される植物全般を意味するアジュガの名で呼ばれることが多いです。
我が家のセイヨウジュウニヒトエは初め、ヘレニウムの脇にて密やかに育っていたのですが、耐陰性に優れているおかげで日当たりが悪い場所にも関わらずスクスクと生長し、いつの間にやら勢力を拡大しておりました。
クリーピングタイムと同様に匍匐性を生かして隙間なく広がってはくれますが、匍匐性植物は過密になると蒸れて元気がなくなる場合もありますので、適度な間引きが必要となります。
草丈は10~30cm程で茎先に総状花序を直立させて青紫色の花をたくさん付けるため、ある程度の高さが必要な場所での利用に向いております。
ネモフィラ


ムラサキ科ネモフィラ属の一年草・ネモフィラ。
ネモフィラの和名は瑠璃唐草(ルリカラクサ)と言い、草丈は10〜20cm程で花茎2cm程の愛らしいお花を咲かせます。
花の色は明るいブルー(園芸品種名:インシグニスブルー)がよく知られておりますが、花弁の先端部が白い黒紫色の品種(ペニーブラック)や、白地に紫色の斑点が入る品種(スノーストーム)もあります。
ネモフィラも匍匐性植物ですのでグランドカバーに適しております。
敷地内の雑草対策としてネモフィラを植えてみてはどうかということで、まずはプランターにて育てて種を作り、その種をばら撒く作戦を立ててみました。
ネモフィラはこぼれ種でも増えるくらいよく発芽するようですので、こぼれ種が混じったプランターの土を空き地にばら撒いてみたのですが、……発芽せず。
ただばら撒けば良いわけではないようですので、作戦を立て直して再度挑戦してみようと思います。


ハイキンポウゲ


キンポウゲ科キンポウゲ属の多年草・ハイキンポウゲ(這金鳳花)。
我が家のハイキンポウゲは八重咲きの園芸品種ゴールドコインで、一般的にはラナンキュラス・ゴールドコインと呼ばれているものです。
草丈は約20cm程で環境が合えばどこまでも広がっていく性質ですので、我が家ではツバキのような高さのある植物の周りに配置しております。
クリーピングタイムのように地下茎では増えずに地上の茎で広がるタイプですので、管理はしやすいと思います。
開花時は花びらがキラキラと輝くように咲き誇りますので、花壇に空きがあるならば、そこを埋めるような使い方もできます。
オルレア


セリ科オルレア属の多年草(1年草)・オルレア。
オルレアは、白くレースで編んだような繊細なお花が約10cm程の塊となって咲きます。
上記植物のように地表を覆うような増え方ではなく、草丈を60cm以上にも伸ばして空間を埋めるような増え方をするため、バラのような背の高い花々の下草(したくさ)として重宝されております。
匍匐性植物のように隙間なく地表を覆うわけではありませんが、その草丈をもって地表付近の雑草の目隠しとなる効果があります。
ただし、至る所に種を飛ばしては芽吹く雑草並みの繁殖力を持っておりますので、人によっては煩わしいと思うかもしれません。
まとめ
今回は「グランドカバーになる植物」についてご紹介しました。
ここまでお読みになった方はお気付きかと思いますが、グランドカバーとなる植物には凄まじい繁殖力が備わっております。
それはつまり、周辺の植物の栄養を奪いその生長を阻害することを意味しております。
特に根で広がる匍匐性植物は、文字通り根こそぎ駆除しない限り果てしなく広がっていくため、どの場所にどの植物を植えるのが良いのか、慎重に検討する必要があります。
我が家では現在、敷地内の孤立している雑草地帯にて、セダムやシロツメクサがどのように生長していくのか実験がてら育てております。
グランドカバーとなる植物は植えっぱなしで手間がかからないと言われておりますが、現在ある雑草より栄えられては本末転倒となりますので、植える場所や使用する植物の種類によっては、放りっぱなしでも良いという訳にはいかないのです。